3
近頃、怪事件が立て続けに起こり、アマガセ国は不安に包まれていた。オギが怪我をした王宮の騒ぎというのも、その一つであった。
かつてこの国は、光の神々の王である太陽神が治めていた。
しかし、やがて光の神々は天界へ引き揚げ、太陽神の子孫にこの国を統治させることにした。その子孫というのが、アマガセ国の王である。
王宮の周囲には、太陽神殿をはじめとする、光の神殿があり、この国を邪悪な闇の勢力から守っているのだが、近年、どういうわけか闇の勢力が力をつけてきているのだった。
その原因として考えられているのが、水晶宮の大巫女の力が弱まってきている、ということである。
水晶宮というのは光の神殿と異なり、闇の勢力を抑えるため、邪悪なるものを閉じこめておくための神殿である。そして、大巫女というのは、その神殿の番人のことである。当然、その番人である大巫女の力が弱まるということは、すなわち、闇の勢力がはびこりやすくなるということであった。
それを防ぐためにも、大巫女は後継者を選び、役目を交代しようとしていた。そして、大巫女の後継者候補の巫女姫たちを、正式に新しい大巫女が決まるまでの間の護衛として、王宮内の兵で護衛隊がつくられたのであった。
護衛隊は、夜がまだ明けない中、水の国へと出発した。
水の国へは、王都を出てから徒歩で三日かかる。しかし、護衛隊の兵士一人一人に馬が与えられていたので、その半分以下の日数しかかからなかった。実際、ユゲたち護衛隊は、出発したその日の夕方には水の国に入り、さらに五日かけて、巫女姫のいる、水の国第一都市エルトゥラに到着した。彼らが、早く目的地に到着できたのは、馬で移動しただけでなく、道中何も起こらなかったことも大いに関係していた。
護衛隊が目指すは、街から少し離れた小高い丘の上の屋敷だった。
時刻は夕暮れである。沈みかけた太陽が、屋敷の白い壁を赤く染めていた。ここからは、屋敷の壁と同じく赤く染められた街並みを一望することができた。
中庭の方から人の笑い声や軽快な音楽が風に乗り、聞こえてくる。宴会が始まるらしい。
この屋敷の主人は、到着した護衛隊を快く迎えた。そして、自分の娘が、この国のために巫女姫候補として選ばれたことを祝う宴を開くから、今晩はゆっくりしてほしいとだけ護衛隊長に言うと、訪れた客の相手をしに中庭へと消えていった。
隊長も、これから離れ離れになる家族の心境を思い、また今から出発するのは無理だと判断して、今夜はここで過ごし、明日水晶宮へ向けて発つことにした。
太陽が完全に地平に沈んだ時、宴はさらに盛り上がった。
宴にはエルトゥラの市長をはじめとする権力者たちが、大勢出席していた。彼らは美辞麗句を連ねて、未来の大巫女の父の機嫌を取っていた。
大巫女は、この国が闇に包まれないよう、邪悪なものを封じる役目を負っている。彼女には、国を統治するような権力こそないが、彼女が持つ、人々に与える影響力は計り知れないものだった。当然、権力者たちは何とかして、つながりを持ちたいと思うだろう。
しかし、ここの姫君も他の姫君同様、大巫女候補でしかないのだった。彼女が大巫女になるかどうかは、誰にも分からなかった。だから、彼らはこの屋敷の主人にしていることと同じことを、他の候補者の親にもしていた。
ユゲは他の護衛兵たちと、屋敷の警備を命じられていたが、隙を見て、さっさと抜け出してきてしまった。
なぜならユゲが唯一楽しみにしていた、この宴の主役はいくら待っても現れず、やっと来たかと思うと、現れたのは侍女で、姫君は気分が優れないとかで、宴には出られないと言うのだ。
それなら、ここにいるのは無用だろう。
ユゲは、巫女姫の護衛兵であるから巫女姫は守っても、脂ぎった欲の塊のような連中を守るつもりなんか微塵もなかった。それに、屋敷の警備なら他でもできる。
宴の様子を窺うことができ、且つ向こうからはこちらの様子がわからないという格好の場所を見つけると、ユゲはそこへ移動した。
つまり、木の上だった。
その木は、大人三人分の太さの幹で、その枝は人一人腰掛けても折れないという丈夫さだった。
そこで、くすねたワインを片手に下を見下ろしていると、宴の開かれている中庭と正反対のところで、黒い影が動いているのがユゲの目に入った。
最初、酒に酔った客が酔いを醒ますために、席を離れたのかと思ったが、どうも違うらしい。
影の向かった先は裏口だったのだ。
影を見失わないように、急いで木から飛び降り、同じように裏口に向かった。
影にはすぐに追いついた。そこでユゲは、その影が初めて女だということに気が付いた。
「どこに行くんだ?」
不意に声をかけられ、女は飛び上がるように振り返った。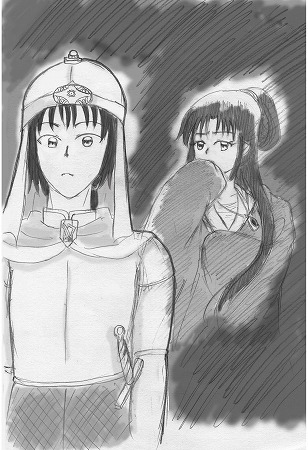
女の長い髪が大きく揺れて、女の体にまつわりついた。
「あなたこそ、ここで何をしてらっしゃるの?」
女は消え入りそうな声で、やっと答えた。平静を装っているが、動揺して、一生懸命落ち着こうとしているのは明らかだった。
「俺はここの屋敷を警備するように命じられている、忠実な護衛兵さ」
夜空を覆っていた雲が切れ、月が顔をのぞかせる。さっきまで影でしかなかった女が、月の光に照らされて、その姿を闇から浮かび上がらせた。
十代くらいの少女だった。黒く、真っ直ぐな髪を、頭の上でまとめていたが、腰まで長さがあるのだから、実際はもっと長いのだろう。それから、質素な着物を着て、黒い布を羽織っていた。しかし、顔立ちの良さから考えると、育ちは悪くないようだ。
何者なのだろう。
「でも、その姿からすると、王宮から来た護衛兵じゃない。あなたたちの役目は、姫君の護衛でしょ? 屋敷の警備はあなたの仕事じゃないわ」
「確かにそうだけど、さっき言ったように、今命令されているのは、この屋敷の警備さ。だから、こんな時刻に裏口から、しかもこっそり出ていこうとする怪しい人間を捕らえるのも俺の仕事の一つなんだ」
少女は一気に青ざめ、慌てて言った。
「私は怪しい者ではありません。この屋敷の者です」
「屋敷の者……ねぇ。この屋敷の者は、主人に奥方、姫君に使用人たちだ。夫妻は、あの広間で客の相手をしているし、執事に言わせれば、今晩は宴に来る客以外、出入りはないそうだ。それに使用人たちの外出には、夜に限り、二人以上で行動することと、執事の許可が必要なはずだ」
見たところ、彼女は一人で、執事の許可も取っていないようだった。
「となると、残るは姫君だが、まさか臥せっている姫君が、こんなところにいるはずもない。それとも、仮病を使って、こっそり抜け出そうとしているのか……。何にせよ、他の人間に確かめればすむことだ。俺と一緒に来てもらおう」
ユゲは連れて行こうと彼女の腕をつかもうとした。
「やめてっ! わっ私は、姫様付きの侍女ですっ。姫様のお使いで、街まで行くだけです」
そう言うと、少女は裏口を飛び出そうとしたが、彼女が出ていくよりも先にユゲが、道をふさいだため、彼女は仕方なく立ち止まった。
「そこを通してっ!!」
ほとんど悲鳴に近い少女の声からは、彼女が焦っているのが感じられた。
「待てよっ。こんな夜中に一人で行くなんて、無謀だ。最近の騒ぎを知らないわけじゃないだろう? 俺が一緒に行ってやるよ」
「結構です。早くそこを通してください」
彼女が姫君付きの侍女かどうか、はっきりしないが、何か悪いことをしに行くような人間ではなさそうだった。
ユゲは、彼女を行かせてあげてもいいと思ったが、近頃は盗賊に魔物、ありとあらゆる魔や悪が出没するから、彼女一人で行かせるわけにはいかなかった。
そんなわけで、彼女との押し問答が、しばらく続いたが、やがて人がやってきて、それを中断することになった。
「ユゲ……こんなところにいたのか。宴はとっくに終わったぞ。今晩は、屋敷の兵に警備を任せて、ゆっくり休んでいいそうだ。早く休めよ。明日も早いんだから」
年輩の兵だった。今まで、まじめに任務についていたのだろうか、彼らはよっぽど疲れているらしく、それだけ言うと、早々に立ち去った。
ユゲも早く、目の前のことを片付けて休もうと思い、少女の方に向き直った。
が、少女は跡形もなく消えていた。
裏口から出ていったのかと思い、外に出てみるが、そこには一面の闇が広がるばかりだった。しかし考えてみると、裏口はユゲがふさいでいて誰も通れなかったのだ。彼女が裏口から出ていったとは、考えられなかった。
彼女はもう部屋に戻ったのかもしれない。
ユゲは、自分の他には誰もいないその場所を後にし、今晩はもう休むことにした。けれど、この奇妙なことが頭の中でいつまでも、もやもやしていた。